閉幕が13日に迫る企画展「藤城清治 光よろこびメルヘン展」は幻想的な影絵が会場の県立近代美術館を彩る。藤城さんは、世界各地で民衆に愛された影絵劇から、独自の境地を切り開いた。光と影で織り成す表現世界は、日本の風土を反映したアートとして再評価の機運が高まる。 (文化部・田尻秀幸)
繊細で色彩豊かな藤城さんの影絵の源流には、素朴な影遊びがあるだろう。日本の絵画に影遊びがしばしば登場するようになったのは、江戸時代の浮世絵。歌川広重や柴田是真らの絵師が、障子戸を使った手影絵や、人物のシルエットを題材にしている。「写し絵」という映像文化もあり、ろうそくを用いた装置で、彩色した絵を寄席などで上映した。
世界に目を向ければ、伝統的にアジアは、精巧な彫刻を施した人形を用いた影絵劇が活発だ。例えばインドネシアの「ワヤン・クリ」という影絵劇は、ガムラン音楽と合わせて上演される。中国やタイ、インドにも古くから影絵劇がある。ヨーロッパでは17世紀頃から記録があり、パリには専用の劇場が複数あった。
猪熊弦一郎といった画家に師事し、全国的な絵画の公募展で活躍していた藤城さんは、終戦後影絵劇に熱中した。影絵の劇団「マオ・カンパニー」を主宰する射水市の日本画家、広田郁世さんは、影絵劇にのめり込んだ藤城さんに共感する。「絵を描いていれば表現にどん欲になる。『ここが動けば魅力的になる』『音楽が付いていたら楽しいのに』と考えるのは自然」。会場に並ぶ初期のモノクロの影絵作品は特に躍動感にあふれ「登場するこびとたちを動かすこともイメージしていたのではないか」とみる。
■80歳で公立美術館へ
藤城さんが公立美術館で初めて展覧会を開いたのは2004年で当時80歳だった。希代の編集者、花森安治と出会い、雑誌「暮しの手帖」に影絵作品を連載し始めたのが1948年。若くして人気を得て、勲章・褒章を受けていたことを思うと意外な気もする。
日本画や彫刻と異なり、芝居から派生した影絵は美術ジャンルの中で評価がまだ定まっていない。例えば図書館で影絵に関連する資料を探そうとすると、行き当たるのはパイオニアである藤城さん自身がかかわった本が大半。大衆的な人気の反動か、藤城さんが美術の専門家から言及される機会も多くはなかった。
■日本列島の風土反映
こういった流れが変わりつつある。ことし完結し、全20巻に及ぶ「日本美術全集」(小学館)は、藤城さんの影絵を取り上げた。最終巻である第20巻のカラーページのラストを彩るのが、東日本大震災をモチーフにした「福島 原発ススキの里」だ。
編集に携わった美術評論家の椹木野衣(さわらぎのい)さんは、直接握ったカミソリによって生み出される身体性あふれる形と、豊かな陰影による叙情性に注目する。「具象と抽象、日本画と洋画、純粋美術と大衆(商業)美術との境界が意味を失った21世紀に、改めて再評価されるべき存在」と言う。
南北に細長い日本という島国は、地域ごとに細分化された特色を持ち、風土を反映した歴史が刻まれてきた。藤城さんは近年メルヘンの世界を出発し「ススキの里」のように全国の地方に取材した作品の創作を活発化させ、厳しい社会の現実にも向かい合う。
「民話や童話、そして手塚治虫、宮崎駿、映画『君の名は。』といった日本の詩的創作には、日本というよりも『日本列島』の風土や自然の過酷さ、それゆえの恵みが両義的に反映されている。藤城さんも震災以降敏感に反応しているように見える」
混迷する世界を反映するかのように、色彩や明暗の複雑さを増す作品について「頭の中だけの夢や幻想ではなく、身体性を伴った叙事詩とも言える」と語る。
全集は藤城さんのページをめくれば、次のような文章で締めくくられている。
「日本美術の未来へ To be continued...」
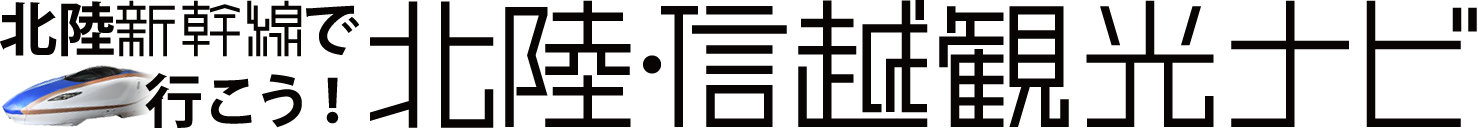







 八尾曳山祭
八尾曳山祭
 八尾おわら資料館
八尾おわら資料館
 樂翠亭美術館
樂翠亭美術館
 有峰湖
有峰湖
 梅かまミュージアム「U-mei館」(見学)
梅かまミュージアム「U-mei館」(見学)
 北日本新聞納涼花火 富山会場
北日本新聞納涼花火 富山会場

