諏訪市の高島城で江戸時代の天明6(1786)年に行われた石垣の修理の様子を再現した立体模型が完成し、9日、市博物館で披露された。石垣を解体して積み直す際、木材を組んで天守閣を支えたやぐらを実物の30分の1の大きさで再現。当時の技術水準の高さがうかがえる。
諏訪地方を中心に江戸時代から活躍する宮大工の流派「大隅流」の業績を紹介する企画展の一環。模型は幅1メートル、奥行き1・4メートル、高さ43センチで、約500本の木を組み合わせている。市博物館の依頼で、大隅流の流れをくむ宮大工の石田喜章さん(63)=諏訪市四賀=と、建築士の五味光一さん(62)=同=が、残されたやぐらの絵図や木材の注文書を基に作った。
石垣修理は、大隅流の礎を築いた高島藩の大工棟梁(とうりょう)、伊藤儀左衛門が指揮。やぐらの上から長い丸太を天守閣と石垣の間に差し込み、建物を支えたと考えられる。石田さんは「力がかかってもやぐらが傾かないようバランスを取るのが難しい。発想と度胸がすごい」。五味さんは「いろいろな建築の専門家に模型を見てもらい、天守閣を持ち上げた方法について意見を聞きたい」と話していた。
模型は来年1月9日まで展示する。
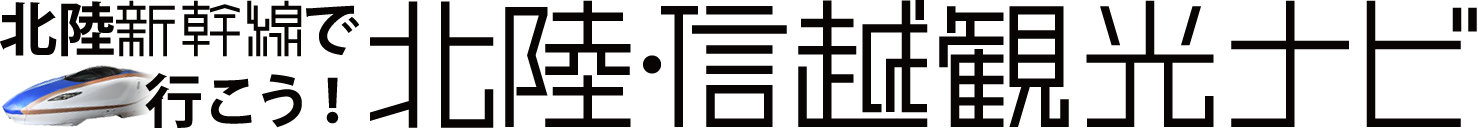




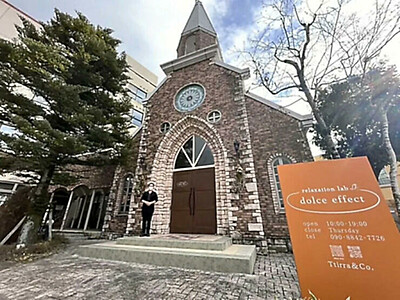


 『ベル・エポックの輝き、オルゴールの調べ』~明るさを取り戻す時代のワルツ~
『ベル・エポックの輝き、オルゴールの調べ』~明るさを取り戻す時代のワルツ~
 しらかば2in1スキー場
しらかば2in1スキー場
 白樺リゾート池の平ファミリーランド
白樺リゾート池の平ファミリーランド
 諏訪湖
諏訪湖
 諏訪大社上社本宮
諏訪大社上社本宮
 諏訪大社下社 秋宮・春宮
諏訪大社下社 秋宮・春宮

