災害と祭礼に焦点を当て、江戸時代の勝山城下町を紹介する特別展覧会が、福井県勝山市の勝山城博物館で開かれている。勝山を襲った水害や疫病、火災と復興の歴史などについて、絵図やパネルなど約60点を並べた。10月3日まで。
「城下町『勝山』~江戸時代の祭礼と災害から探る~」は、同博物館と勝山市の共催。城下町の歴史や暮らしを紹介し「勝山は江戸時代にもさまざまな災いを乗り越えて来た。コロナ禍も乗り越えよう」との思いから、災害と祭礼をクローズアップした。
毎年のように城下町を襲った洪水については、災害前後の町並みを描いた絵図を展示。1707(宝永4)年の松原新道図は古い道が途切れ、新しい道が作られていることから、洪水後の復旧工事が反映されていると考えられている。
また、勝山では1859(安政6)年に流行したコレラの対策を紹介。当時は「魑魅魍魎(ちみもうりょう)」だと考えられ、音で追い払おうと大砲10発が放たれた。展示では、77年ごろの絵図上に大砲を撃った場所や順番、方向を示した。
死の恐怖や災いから逃れようと社寺に参った人々によって行われた祭礼については、左義長と御前相撲を紹介。67年から7年分の左義長収支決算帳や明治時代に作られた押し絵などを展示している。
12日午後1時半から、県埋蔵文化財調査センターの職員らによる講演会「勝山城下町の発掘最前線」がある。定員30人で、事前申し込みが必要。問い合わせは同博物館=電話0779(88)6200。
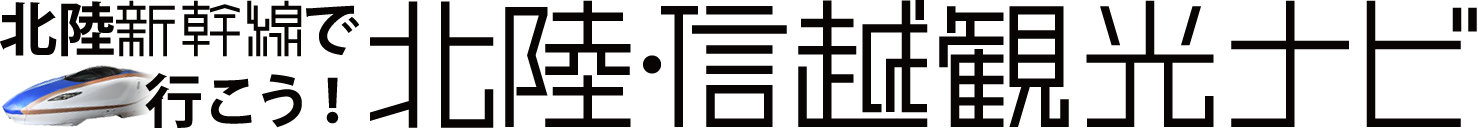







 第20回勝山恐竜クロカンマラソン
第20回勝山恐竜クロカンマラソン
 ダイノシアター
ダイノシアター
 小池公園
小池公園
 国民宿舎 パークホテル九頭竜
国民宿舎 パークホテル九頭竜
 七間朝市
七間朝市
 スキージャム勝山
スキージャム勝山
 寺町通り
寺町通り

