23日に七尾市の県七尾美術館で開幕する「長谷川等伯展」(北國新聞社後援)で、国宝「松林図屏風(しょうりんずびょうぶ)」の原形とされる「松林架橋図襖(しょうりんかきょうずふすま)」(京都市・樂美術館蔵)が北陸で初めて公開される。等伯の繊細さと豪快な筆遣いを堪能できる作品18点が一堂に会し、多彩な画法に取り組んだ画聖の魅力を伝える。
「松林架橋図襖」は、「松林図屏風」の7年ほど前の作とされ、等伯が大徳寺の三玄院に勝手に上がり込んで描いた名作「山水図襖」(京都市・圓徳院所蔵)と同じ襖の一部に描かれている。
北原洋子学芸員は「松の幹の曲がり方、枝ぶり、筆を置いてから跳ね上げる松葉の描き方が類似している」とし、日本水墨画の最高峰と名高い「松林図屏風」につながる作品であると指摘した。会場には「松林図屏風」の複製も並び、比較して鑑賞できる。
同じく北陸初公開の「四季柳図(しきやなぎず)屏風」(個人蔵)は6曲1双の大画面に大胆に柳の木を配し、若葉が芽吹く春から、葉を落とした枝に薄く雪が積もる冬景色を表現する。
等伯は1539(天文8)年、七尾に生まれ、30代で新たな活躍の場を求めて京都へ移住した。展示会は「水墨・濃淡の妙VS着色・彩りの美」をテーマとし、能登時代に描かれた仏画や上洛(じょうらく)後の装飾性の高い金碧画(きんぺきが)、晩年の精緻な水墨画など多彩な作品が並ぶ。
七尾初公開となる等伯の次男宗宅の作品「李白・陶淵明図屏風」(京都市・北野天満宮蔵)、長谷川派絵師の作品も紹介する。
5月22日までで、30日午後2時からは北原学芸員による作品解説が行われる。
長谷川等伯を顕彰する「等伯会」は5月4日、県七尾美術館で直木賞作家、安部龍太郎さんの特別講演会(のと共栄信用金庫共催、北國新聞社、ラジオななお後援)を開く。
長谷川等伯展に合わせたイベントとなり、安部さんは直木賞を受けた小説「等伯」をテーマに、七尾や等伯との縁を語る。
聴講は事前予約が必要で、等伯会の会員以外の一般参加も受け付ける。定員は100人程度で入場無料。開演は午後2時。問い合わせは市スポーツ・文化課内の同会事務局まで。
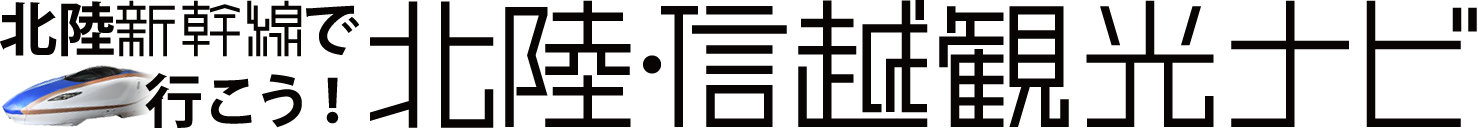







 道の駅 能登食祭市場
道の駅 能登食祭市場
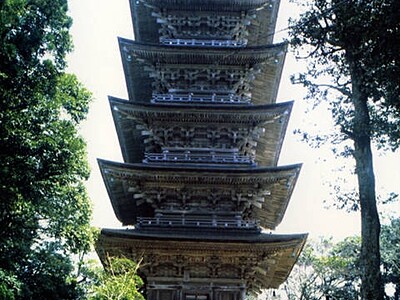 妙成寺
妙成寺
 和倉温泉
和倉温泉
 気多大社
気多大社
 能登島
能登島

