-

さぁ春スキーシーズン到来! 奥只見丸山スキー場(魚沼市)3月20日オープン、5月ごろまで滑れます♪
新潟日報 2024年3月18日
-

ライダー誘客へタッグ 魚沼市観光協会とバイク用品販売「デイトナ」(静岡県)がパートナー協定 バイクイベントで観光振興に力
新潟日報 2024年3月11日
-

緑色がお内裏様、ラベンダー色がおひな様 ヒスイ用いた見立て雛、糸魚川市で展示会
新潟日報 2024年2月27日
-

「あちこたねぇ」=心配ない 「じょっぺんなんな」=調子に乗るな 魚沼市の永林寺で方言使ったおみくじ 全部で22種類
新潟日報 2024年2月21日
-

カレーにタコス、焼きそば...屋台グルメが大集合! 「ゆざわナイトマルシェ」JR越後湯沢駅東口で1月19、20日開催
新潟日報 2024年1月17日
夫婦円満などを願い、新婚の花婿に水を浴びせる奇祭「雪中花水祝(はなみずいわい)」が11日、新潟県魚沼市堀之内の八幡宮で行われた。上半身裸の花婿11人が必死の形相で冷たい水に耐える姿に、観客からは祝福の歓声が上がっていた。
江戸時代に鈴木牧之が「北越雪譜」でも紹介している伝統行事。明治時代に入って途絶えたが、1988年に地元商工会の有志らが復活させた。過去2年は新型コロナウイルス禍のため見送られ、3年ぶりの開催となった。
この日は、日が暮れつつある午後5時半過ぎ、クライマックスの「水祝の儀」が始まった。水は元日午前0時にくんだものに、イタドリの花を加えた「花水」が用意された。
11人が1人ずつ雪上の舞台へ上がり、四つんばいになり、背を空に向けて構えると、左右の男性6人が容赦なく水を浴びせかけた。花婿が「冷たい」「ありがとうございました」と声を上げると、大勢の観客から歓声や拍手が湧いた。
昨年5月に結婚した魚沼市堀之内の男性会社員(48)は「地元で生まれ育ったので祭りに参加できてうれしい。水は冷たいというより痛かった。家族で健康に暮らしたい」と、すっきりした表情で話した。
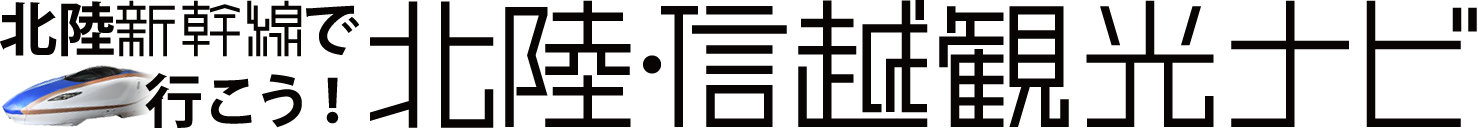


 苗場スキー場
苗場スキー場
 苗場ドラゴンドラ
苗場ドラゴンドラ
 ぽんしゅ館 越後湯沢驛店 酒風呂
ぽんしゅ館 越後湯沢驛店 酒風呂
 ryugon
ryugon
 雲洞庵
雲洞庵

