江戸時代を中心に、福井県内の川と人の営みの関わりを伝える「描かれた川と人々~越前・若狭の利水の歴史~」(福井新聞社後援)が福井市の県立歴史博物館で開かれている。貴重な地図や絵図など計77点を通し、生活用水や農業用水だけでなく漁業や物流などで幅広く利用されていた歴史を紹介している。26日まで。
県内最大規模の農業用水、十郷用水の1842(天保13)年ごろの取水口周辺を題材にした「十郷用水樋埋仕方大方之図」は、九頭竜川を無数の竹や石でせき止める工法や舟に乗る人々、川沿いの家並みなどを詳細に描いている。
1862(文久2)年の「川除普請と乾季日野川絵図」は、流量が極端に少なく水たまりがいくつか並ぶだけの時期と通常時の様子を並べ、当時は水位などが観測できず記録しにくかった渇水の状況を伝えている。
このほか、福井城の城下町の用水を舟で下ってきた人が階段を使い料亭に入る姿や、連続する堤防をあえて途切れさせて近隣の水田などに水を逃がす「霞堤(かすみてい)」の位置をしるした絵図などが並ぶ。
25日に学芸員による展示解説がある。予約不要。
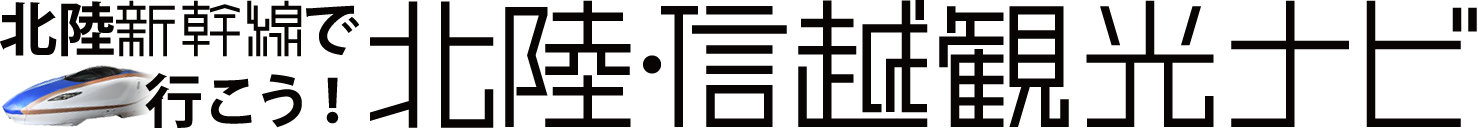







 アスリート・ナイト・ゲームズ・イン・フクイ
アスリート・ナイト・ゲームズ・イン・フクイ
 特別展「橋本左内と横井小楠」
特別展「橋本左内と横井小楠」
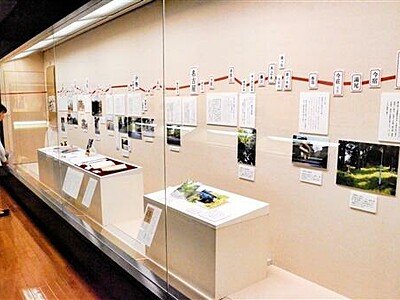 江戸時代の旅 曙覧の旅
江戸時代の旅 曙覧の旅
 和傘スカイ
和傘スカイ
 付箋アート
付箋アート
 チーズ専門レストラン RUNNY CHEESE(ラニーチーズ)
チーズ専門レストラン RUNNY CHEESE(ラニーチーズ)
 ラーメン門
ラーメン門
 LeBRESSO(レブレッソ)福井店
LeBRESSO(レブレッソ)福井店
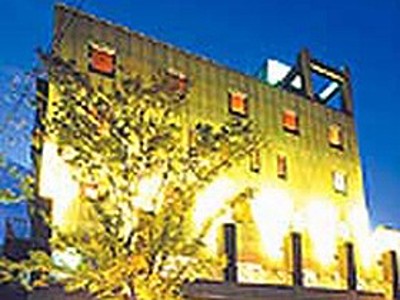 若杉
若杉
 ラーメン山岡家 福井大和田店
ラーメン山岡家 福井大和田店

