-

上高地、河童橋のたもとは観光客でにぎわい 雪解け早い北アルプスを背景に開山祭 松本市安曇 【動画付き】
2024年4月28日
-

ご当地グルメ・牛乳パン12種類をカプセルトイに 長野県内各店のパッケージを再現、松本市と銀座NAGANOで販売
信濃毎日新聞 2024年3月23日
-

春めく信州、爽やかに 松本ランニングフェスに1067人・100組 信州スカイパーク
信濃毎日新聞 2024年3月17日
-

2代目「なぎさTRAIN」出発!イラストいっぱいのデザイン ピンクのハート型の持ち手引き継ぎ アルピコ交通がお披露目
信濃毎日新聞 2024年3月15日
-

牛の張り子に雪を投げ、響く笑い声 五穀豊穣を願い「お田植祭」 筑北村の刈谷沢神明宮
信濃毎日新聞 2024年3月4日
松本藩主として松本城の天守を築いた石川数正、康長親子の法要が11日、松本市大手5の正行(しょうぎょう)寺で行われた。康長が身近に置いて拝んでいたという「念持仏(ねんじぶつ)」が、1971(昭和46)年に福岡県の石川氏の子孫から松本市に寄贈されたのを受け、73年からほぼ毎年、康長の命日に行われている。市民有志や愛知県に住む石川氏の子孫ら計約60人が参加し、功績を振り返った。
念持仏は木彫りで高さ約30センチ。康長は1613(慶長18)年に江戸幕府の改易で九州に移って以降、42年に亡くなるまで毎日、この念持仏を拝んだとされる。現在は松本市立博物館が所蔵する。
住職の佐々木一男さん(58)が念仏を唱える中、参加者が次々に焼香した。愛知県内の石川氏の子孫らでつくる「三河石川会」の石川武さん(73)は「多くの人に参加してもらえて、先祖が立派な人物だったことを改めて実感した」と話していた。
「康長の松本への思いを想像しながら念仏を唱えた」と佐々木住職。「(法要参加が)松本城や城に関わった先人に興味を持つきっかけになればいい」と話した。
松本城管理事務所の研究専門員による講演もあった。
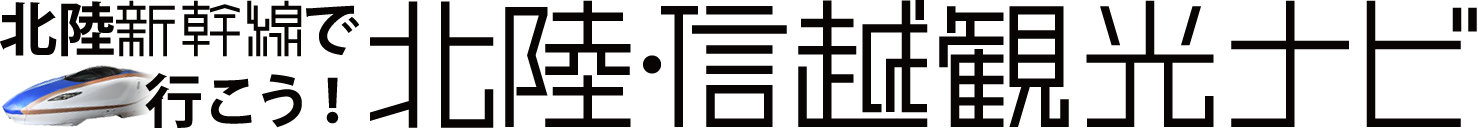


 上高地
上高地
 旧開智学校
旧開智学校
 白骨温泉
白骨温泉
 信州松本野麦峠スキー場
信州松本野麦峠スキー場
 大正池
大正池

